(過去の記事)
カンボジアの孤児院や学校と関わってて必ず言われるのが「寄付をしてください」ということ。中には孤児院への入場料もしくは見学料というように、お金を払わないと追い払われるところもあるらしい。
そうなった事情も、理解しなければいけないんだけどね。
①孤児院を閉鎖するという決定があったこと
②写真だけ撮って、寄付を募り、そのお金は孤児院まで届かないケースが多いこと
①孤児院を閉鎖するという決定があったこと
カンボジアの孤児院の数は269(2010年時点)。分かっているだけでこれだけあるということは、本当はもっと多いんだろう。
孤児院って言っても種類があって、
(1)両親がいない孤児のためのもの
(2)両親が暴力を振るったり、あるいはネグレクトされる子どものもの
(3)両親に子どもを育てる経済力がなくて預けられる子どものもの
(3)のケースが多いみたいで、私の知ってるところもこのケースが大半。
こういった孤児院が監査を受けて、適当でないと判断されると、閉鎖される。
そうならないために、孤児院の経営者は今必死になって、孤児院の改築や整備に力を入れている。
孤児院の子どもの毎日三食の食事だって大変なのに、そんなことまでするとなると、今まで以上にお金がかかるのは目に見えてる。
②写真だけ撮って、寄付を募り、そのお金は孤児院まで届かないケースが多いこと
どういうことかというと、ある人が孤児院を訪問して写真を撮り、勝手にその写真を自分のホームページで寄付を募るために使い、結局そのお金はどこへいったのかはっきりしないということがよくあるらしい。
そういう愚痴を聞いていると、結局、寄付してもらえるだろうという気持ちで孤児院でも学校でも始めたんでしょって考えざるを得なくなり、いつも悲しい気持ちになる。
写真を悪用した人が悪いんだけど、結局人は自分の生活が守られ、満たされることが一番大事なんだっていうことを象徴する話のような気がする。そしてそれには限度がないんだ。
孤児院や学校の経営者がなぜ孤児院や学校を始めたのかって理由として、もちろん崇高な志があったということは、言うまでもないことなんだよ。
自分が子どもの頃、(クメール・ルージュの時代の後)難民キャンプで貧しい暮らしをしいられていた。 そんな思いは現代の子どもにさせたくない。

ともあれだから「寄付」なんだけど、私たちはどうやって付き合っていったらいいのだろうか。
日本人と違って、欧米人は、どちらかというと寄付に寛大で、喜んで寄付をするように思う。日本のNPOは会費で運営されているものが多いが、欧米のものは寄付のみでの運営がよく見られる。それはNPOに限ったことではなくて、研究所や病院なども、寄付で建って運営されてしまう。
それからカンボジアやタイでも、貧しい人には施しを与えるという傾向が見られる。これは上座部仏教の教えによる“喜捨”っていう考え方に表れてて、そのような行いは、死んでから天国へ行けますよ、と信じられている。托鉢もここからきてるよね。
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教…貧者救済のための“喜捨”という精神は、聖書の中でも説かれているらしい。
喜んで捨てますよ。喜んで与えますよ…・
世界的にもまれに見る宗教に寛大な日本という国で生まれ育った私には、神様の教えを信じるっていうことにやっぱりどうしても違和感。簡単に理解できないんだよ。
私が好きな映画に「Eat Pray Love」っていうのがある。主人公である女性(アメリカ人)がイタリア、インド、インドネシア(バリ)を旅して人生を見つめ直す話。バリで出会った薬屋さんの親子が、自分たちの家が欲しいという話をする。主人公は友達にメールを送り、事情を説明して、その友達は彼女のメールに心動かされて小切手を切る。2,3日の間に家が建てられるくらいの寄付が集まり、薬屋さんの親子は家を建て始める。
こういう一時的な支援は一見美しい話に聞こえるけど、その後はどうなるのかなって心配になるよ。
最近やっと見た映画「僕たちは世界を変えることはできない」という話。(私が日常で見てる景色そのものだった!)これは大学生がカンボジアに学校を建てた話というよりは、150万円を集めた話といった方がしっくりくると思った。学校を建てることですべての子どもが学校に行くことができるわけではないという、一番の問題点が、結局どう解決されたのかが分からなかった。今日を生きるために、親を手伝って働きに行かなければ行けないということは、この国のどこにいても起こる。
日本人である私が目指したいのは、持続可能な経営ができるようになる人材の自立支援なんだ。だけど寄付のように結果がはっきり表れないし、長期的な計画であるから、なかなか理解が得られない。
どれだけ考えても答えのない問題に、首を突っ込んでしまったようで、これから一生この問題に悩み続けるのかと思うとため息が出る。
時代の状況や、国際社会の一国としての立ち居地によって、次の一手は変わってくる。
そのときに出した結論にくっついてくる結果がきっと答えだろう。
寄付を否定しているわけじゃない。今後、その市場は今よりもっと大きくなっていくと思う。
寄付とは人の感情や努力や希望のこもった大切な一つの手段だ。
格差の激しい社会には、有効な方法なんだ。
一時的な援助もその瞬間の壁を突破するためには必要だ。
でも目指したいのは、その先。
当事者が、自分の力で生み出し、考え、継続していく力を一番大切にしたいと思う。
「寄付がもらえない」と嘆くのではなく、自力で運営する方法を考えるようになっていったら嬉しい。

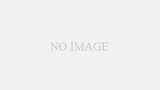
コメント