(過去の記事)
シェムリアップの町から北へおよそ30キロメートル。
途中、アンコール・ワットの前を通り過ぎ、アンコール・トムの中を直進。
そのままずっと北へ、青い空と赤茶色の大地、生い茂る緑の木々で目を潤しながら、
その間を爽やかに吹き抜ける風を感じ、トゥクトゥクにゆられること約1時間。
「伝統の森」と呼ばれる、一人の日本人がつくった“村”があります。
この村に住む約200人のほとんどが、カンボジアの伝統の絹織物の作成に従事しています。
蚕を飼い、桑の葉を育て、糸を引き、自然の染料で糸を染め、染めに使う植物も育て、手作りの折機で布を織り、その布を売って生計を立てる。
一つの村が一枚の極上の布を織り上げるために機能している、といったところでしょうか。
先日、様々な理由や縁があり、この森をつくり、現在も森で暮らしている、森本喜久男さんに会いに行くことができました。
カンボジアの伝統の織物の復興のために、20年以上も尽力されている方です。
実は「伝統の森」を訪れるのは今回が2度目。
前回は、3月の満月の日、これもまたありがたいご縁があって、「伝統の森」で開催された「蚕祭り」行くことができました。
「蚕祭り」とは、糸を引くときに蚕を殺生することを供養するということに起源を発し、2日間開催されるお祭りで、1日目はこの村で作られた絹の布を身にまとった住人が特設のランウェイを歩く、ファッションショー。
2日目が蚕の供養です。
ファッションショーの写真をお見せします。

マイクを持っている方が森本さん。

子どもから大人まで、それぞれが個性的で目を見張るような着こなし、身のこなし。
堂々とランウェイを歩いていました。
こんなに素敵な着こなしが、たった数枚の布から表現されているのかと考えると、思わず見入ってしまいます。
また、メイクやヘアアレンジも、モデルさん(住人)それぞれの魅力を引き立てます。
さて、今回は、「伝統の森」を案内して見て回ったこともそうですが、
20年…多分それ以上の歳月が育んだ、カンボジア伝統の絹織物の父である森本さんと貴重なお話、相談にのっていただきました。
私の中で噛み砕いて整理した形にして、少しだけ紹介します。
□人を動かす ~約束や責任を相手に分かってもらう~
“約束”や“責任”、言葉にすると一言ですが、それの中身を全うさせるには、それをすることでその人のメリットになるのか、ということを考えて与えないといけない。それがその人が生きるために必要な行為なら、絶対にやる。そのリアリティーを感じさせることができているのか。(リアリティー=実感;話の中や著書の中で何度もリアリティーと言う言葉が出てきたので、そのまま使用。)
□人との関わりはGive and Take
自分が欲しいものだけを求めすぎてはいないか。相手が欲しいものを十分与えることができているか。関係が崩れるのは、自分がTakeばかりだったということ。
親子、友人、恋人、教師と生徒の関係だったら、どちらかがGiveばかりでも程度の差はあれ許されるのだろうが、働く人と人の場合は、GiveとTakeのバランスが非常に大切。
□本気の志 ~他人を信じるか・疑うかは問題ではなく、自分を心から信じているか~
自分のしようとしていることは、心の底から叶えたいことなのか。本気でその夢の実現を想って、考えているのか。自分が本気の志を持って動いているなら、相手にもそれが伝わり、動いてくれるはず。
私は、文化や習慣の違うカンボジア人と、共に生きること、特に働くことという視点で相談をしたのですが、自分の中でその言葉を反芻することで、何もカンボジア人に限った話ではなく、日本にいたって、他人と共に生きるという場面に置き換わるということに気付きました。
話をして、自分の中でストンと納得がいったものは、今からの挑戦に、大いに活かしていこうと思いました。
最後に、「伝統の森」への行き方は、シェムリアップ市内のショップ兼工房に寄って、トゥクトゥクドライバーさんに場所を確認してもらってから出発すれば、確実です。
自然にあるものだけで染めた深い色
職人の呼吸が波打つ布
100年の伝統を甦らせた柄
シェムリアップにお越しの際は、ぜひ寄ってみてください。
声掛けていただければ、ご案内しますよ。
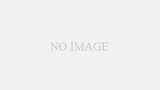
コメント