(過去の記事)
国民性を表したジョークってたくさんあって、その中の一つにこんな話がある。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
ある船が沈没しそうな状況にある。
女性と子どもは救命ボートに乗せるとして、
男性の乗客を、海に飛び込ませないと船は沈没してしまう。
船長がかける言葉、
アメリカ人には「ヒーローになれますよ。」
イギリス人には「紳士だと認められますよ。」
ドイツ人には「ルールですから。」
イタリア人には「もてますよ。」
日本人には「みんなも飛び込みますよ。」
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
最初に聞いたときは、笑ってしまったこの話。
たまに、実感と共に思い出すことがある。
実際に私が体験したこんな話もある。
友達とたまにする、何で今の専攻(大学などの)を選んだのかという話。
アメリカ人は「難しくてやりがいがありそうだったから。」
カンボジア人は「簡単で自分にできると思ったから。」
日本人は「家族がみんなその道の人だから。」
そのままジョークになりそうだと思った。
自立を評価する社会、
躓くと戻ってこられない社会、
世間体が個人の価値を決める社会。
これが今の自分に見えている世界。
日本では、大学生の就職活動の時期がまた遅くなり、4年生の4月から始まるということ。(2015年当時)
今までの12月からの空白の4ヶ月を、企業のインターンシップにあてる傾向にあるとか。
インターンという片仮名にすっかり本来の意味が見えにくくなってしまっている。
私は海外にいたときに本当のインターンの意味を知った。
「日本のそれはインターンじゃないよ。」と言われた。
会社から「こんなことできますよ。」
って呼びかけるのではなくて、
学生が「将来こんな仕事がしたいから、こんな会社で働く経験がしたいです。」
って求めるもの。
和製英語はたくさんあるけど、この“インターン”ってなかなかひどいもんだ。
70年前の人たちが描いた未来はこんな未来だったのか?
10年後の未来もこんな未来なのか?
もっと、選べるんだから、選んでいいはずなんだよね。
どこの国をどうだって批判するつもりは全くなくて、
ただの自分の考えなんだけど、
恩があるからって人の顔色を伺って、
可能性に蓋をしてしまう社会の構造は、
とってもやるせない。
簡単に今あるものを捨てられないことも分かってるけど、
空いた手で掴める、新しい未来の可能性を思い描く、
思い描くことを認める社会があるなら、
それが理想。
それが私が自分の未来を創っていきたいと思う場所。
それを創っていけるのは、愛国心…?
そう考えたら、まだ全く自分の責任を果たせてないや。

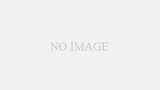
コメント