(過去の記事)
カンボジアでは毎年9月下旬から10月上旬のどこか3日間、Phcum Ben(プチュン・バン)Celebrationという1年で一番大きな祝日となります。
聞くところによると実際の祝日になる前の2週間ぐらいをsmall celebration(小さなプチュン・バン)と呼び、確かに平日の割にはざわついてるなあと、お祭りっぽくなります。
毎朝パゴダ(お寺)では朝の4時から多くの人が集まって、先祖に感謝を伝えたり、お布施をして自分や家族の健康や幸運を祈ります。
お寺ではお米を投げたり、ご飯をお供えしたりします。
プレッドという先祖の魂にご飯を与えることで、
こっちの世界に帰ってきてはいけないよ、という意味があるそうです。
なんだかどこかで聞いたことあるような話!
日本でいうお盆ですね!
そんなことがあるため、その時期は毎朝4時に、イスラム教国家のアザーンのような音がスピーカーから流れ、シェムリアップ市内中に響き渡っているそうです。
が、しかし…
「そんな音聞いたことないよ?」って言ったら
カンボジアの人たちが、
「うそぉ?!笑 しっかり眠ってるんだね…笑」
って笑われました。
毎朝6時半に起きてても、こっちの人たちは
「やっと起きたの。」
って目で見てくるし、
「起きるの遅いねー。」
って子どもに言われるし、
町は朝から人で溢れていて、もうみんな7時半には一仕事終えたような顔をしています。
(公立の学校は7時から始まります。)
日暮れとともに眠り、夜明けとともに起きる。
村の住民だけではなく、町に住む人も、
今まで会ったカンボジア人すべてがそんな生活をしています。
それが、日本人との最大の違いだな、と思っています。
さて、私がカンボジアで活動をしている教育支援団体ティスタには、
「先生が不足している学校で先生をする」
というコンセプトがあります。私たち日本人の力は多くの場所で求められています。
先生が不足している学校はたくさんありますが、そのような学校の多くは町から離れた村に多いです。
そのため、私が教えている場所も、町から少し離れた貧しい村なんです。
その学校に通う子どもたちも貧しい家の子どもたちがほとんどです。
「貧しいってどんな生活なんだろうか」
料理の上手なNGOの学校のお母さんに連れられて、家庭訪問について行きました。
今回は私が見た村の生活の一部を紹介します。

まずはこちらの小さな家。
家の周りはごみで溢れていました。
お母さんと子ども3人の4人暮らし。
お父さんは恋人を作って家を出て行ってしまいました。
お母さんが一家の支えとなるため、
一日の半分でごみを集め、一日の半分でごみを売るという生活をしているそうです。

こちらは子どもだけの2人暮らしの家。
両親はそれぞれ恋人を作って出て行ってしまったとか…。
お兄ちゃんは勉強が好きで、公立の学校には行っているようです。
弟は自閉症で一人で生活ができません。
お兄ちゃんやまわりの家族が面倒をみてなんとか生活をしているそうです。
川沿いの家は政府の開発計画によって、現在立ち退きが通告されています。
この家も、観光の主要道路と平行して流れている川の上にある家。
「行く場所はわかっているのか?」
と聞くと、
「分からない。出て行かなきゃいけないことは分かっている。」
ということでした。


これも川沿いの家。
お父さんと、子どもが2人と、最近赤ちゃんが生まれたばかりです。
お母さんはこの子を産んで、亡くなりました。
お父さんは元々軍人の仕事をしていますが、
今は赤ちゃんの世話のため、働きに出かけられません。
ミルクだけは欠かさず赤ちゃんに飲ませようと、
周りの家の人も協力して赤ちゃんを育てていました。
この家庭訪問はNGOのお母さんが定期的に行っていることで、
ほとんどの村の住人のことを把握しています。
定期的に足を運んで、子どものいる家庭には、NGOの学校で勉強するようにと話しています。
生活に窮している家庭には、土地を低金利で貸して、農業のやり方を教えています。
実際にそれぞれの家庭を見て思ったことは、
学校に来れている子どもたちはまだまだ恵まれている子どもたちなんだろうなということでした。
村では、見たことのない子どもの顔をたくさん見ました。
学校に来ていない子どもたちの親は、
子どもが勉強をすることの必要性を知らないため、
学校に行かせようとしません。
子どもには働いてもらわないといけないのです。
学校に来なくなったなーと思うと、親と一緒にマーケットで働かなければいけなくなったという子を何人も見てきました。
このようにして差が生まれていくのだなと感じました。
この日の帰り道、いつもの道とは違う、村の中の道を通って帰りました。
外国人はめずらしいのか、村の人たちの目線を痛いほど浴びました。
Hello.と手を振られることもありました。
子どもたちの集団の横を通り過ぎたとき、
一人の男の子が自転車の後ろに乗ってきました。
最近習得したての自転車二人乗りの前役なので、
背中に背負っていたバックパックを気にしながら、
焦りながらも必死ででこぼこ道をこぎました。
その子を降ろすと、前に出てきて、私の行く手をふさぎ、
「あんにょんはせよ?」と言います。
それに対して
「No, こんにちは」と言い返します。
「ろいっ、ろいっ、ろいっ」
と言って手を出してきました。
(あーぁ、分かってしまった。)
“ろい”はクメール語でお金を表します。
分からない振りしかできなかったのが情けなかった。
こんなときはどうやって応えれば良いのか…。
結局、英語も話せないようだったので、
あきらめて道を通してくれました。
カンボジアには、いつも見ている純粋な笑顔ばかりではないということも、
ここで暮らしていると感じることがあります。
でもどの人もみんなそれぞれの基準で必死で生きようとしていることは確かです。
それはどこで生きていても同じだなと思います。
ティスタとして活動をしながら、自分のいる国の見えにくい側面を見た一日でした。
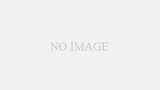
コメント