リトミックとは
そもそもリトミックとは、元々はスイスの音楽学校で音楽学校の生徒のために開発された音楽教育法らしいのですが、日本では幼児教育の一つの方法だと多くの人からは認知されています。
音楽に合わせて体を動かすことで子どもの脳が刺激され、音楽の能力だけでなく、人間の創造性、主体性、人格形成に関わる要素を育成することが期待されています。

英語リトミックに通わせようと思った理由
リトミックをなぜ英語でやるのか。
私は”英語リトミック”と聞いたとき、
興味のある2つの要素が1つになっていてとってもお得!
と思いました。
まず英語リトミックに通い始めた頃、ちょうど私が児童英語教師の資格取得のための勉強を通信教育で行なっていました。
最終課題のレポートのテーマを”リズムやダンスを英語教育に取り入れること”として資料を集めていました。
とのとても良いタイミングで、英語リトミックについて知りました。
そもそも”英語”は家で一緒に歌や絵本を読んだりして親しんではいるけど、やっぱり英語ネイティブの英語は聞かせたいなと考えていました。
英語を日本語のような”会話”だと認識してほしいと思っていたからです。
そして幼児や児童の英語教育に興味のある私も、赤ちゃんの時期なら子どもと一緒に教室に潜入できるので、自分の勉強にもなると、邪な考えも持っていました。
ただ赤ちゃんのうちから英語教室に通わせるのは、勉強を押し付けているようで気が引けました。
そこで、リトミックならリズムや音楽に合わせて体をたっぷり動かして、音楽の感覚を早いうちから”楽しんで”身に付けることができます。(音楽の感覚は、体を自分の思う通りに動かすことができるようになるという、スポーツの素地を作ることにも関わってくるそうです。)
それに加えて英語ネイティブの英語のシャワーを浴びることができます。
一石二鳥だと思いました。
半年通って見た子どもの教室での様子
息子が初めて教室に行ったのは、1歳になる月でした。
人数:2組〜8組ほど(同じくらいの月齢の子どもとお母さん)
時間:30分/1回
回数:3回ほど/1か月
人見知りで、あまり大人数が得意ではない息子は、教室に入るなり泣いていました。
クラスが始まって、泣き止んだとしても、緊張して固まっていました。
毎回毎回そんな感じでした。
たまに調子の良い日があると思って安心しても、次の週にはまた泣いての繰り返しでした。
この子には向いていないんじゃないかと思って、あんまり嫌がるようであれば無理に続ける必要もないと考えていました。
泣かない!楽しんでいる様子に変化
大きな変化を感じたのは英語リトミック教室に通い始めて6か月が経ったころでした。
やっと泣くことがなくなってきたと感じていました。
家では毎日のように教室で使用する音楽をかけ流しています。
音楽については慣れたものが多いはずです。
音楽だけでなく、先生にも慣れてきました。
今までは怖がっていた(ように見えていた)ネイティブの先生にも怖がらなくなりました。
ちゃんと先生を見て、動きを真似しています。
先生が息子に正しい動きをさせようと手を差し伸べても、それを受け入れています。
具体的に変化していったことといえば…
①2本のスティックを持って、太鼓のように床を打ち鳴らす
→ピアノの低い音でスティックを下の方に持っていき、打ち鳴らす
→ピアノの高い音でスティックを上の方に持っていき、バンザイのような動作をする
→バンザイの動作からだんだん2本のスティックを打ち鳴らす動作ができる
②タンバリンを持ってピアノの音楽に合わせて速く走ったり、ゆっくり走ったりする
→タンバリンをピアノのリズムに合わせて上手に叩く
→タンバリンをピアノの速い遅いのリズムに合わせて叩き分ける
③スカーフを持って先生の動きを真似する
→スカーフを顔にかぶって”peek a boo”に合わせて”BOO—“とする
→スカーフを”shake”で振って、”swing”で揺らす
→スカーフをくるくる丸めて自分の手の中に収める…(←まだできません)
④音楽に合わせて体を動かす
→”brush your teeth”や”wash your face”の動作をする(←家ではやるけど気分が乗らない日は教室ではやらなかったり…)
息子は歩いたり走ったりするのがとにかく好きなので、歩いたり走ったりの動きがある曲の方が得意です。
座ってやるようなものは、日によってはまだ先生を眺めているだけの日もあります。
音楽を司る機能は0歳から鍛えられる
モンテッソーリ教育や、脳科学と教育の本などを読んでいると、子どもが強く興味を示し、それを習得するのに一番適した時期(敏感期)があるということです。
例えば、運動は生後6か月から4歳ぐらいが敏感期にあたるので、その時期にその子の発達にあった動き(歩く、走る、ジャンプする、手先を使う等)を十分に行うことで、その後の人生の運動能力を決める基礎を培うことができるようです。
言語はお母さんのお腹の中にいるときから周囲の音を聞いていますが、生後7か月から5歳半までに母語の基礎をどんどん習得するようです。
参考「0-3歳までの実践版モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!」
音楽も周囲の音を聞くという意味では言語と同じく、0歳からが適しているということになります。
特に、体をある程度自由に動かすことができるようになった子どもは、音楽を聴くと、それに合わせて好きなように体を動かします。
息子はリトミックのおかげか、毎日生活の中に音楽をかけ流していたおかげか、1歳4か月ぐらいから音楽を聴くと、自然と体が動くようになりました。
歌や踊りだけでなく、タンバリンやマラカス、トライアングルなどの簡単な楽器にも興味を示し、時間を見つけて親子で演奏することもあります。
息子がリトミック教室に楽しく通っているので、しばらく様子を見ながら続けたいと思っています。
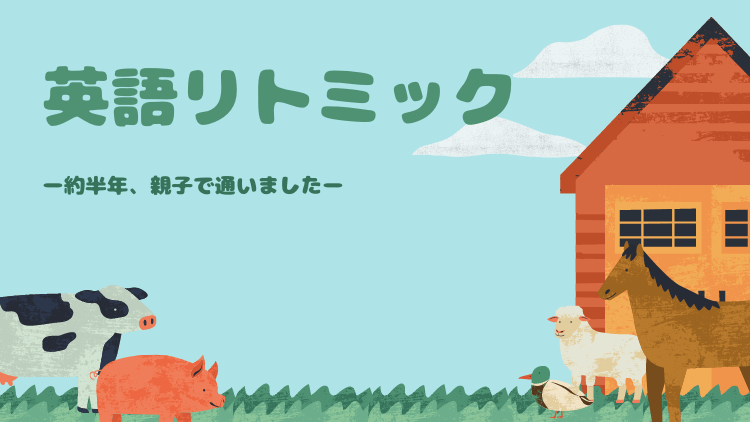


コメント