幼少期からの適切な教育によって人生が変わる
「幼児教育の経済学」という本を読みました。
ジェームス・J・ヘックマンという経済学者の方が、経済の視点で教育について書いた本です。
幼少期の介入が変化をもたらす
人の人生を決定づけるのは遺伝子だという研究があります。
反対に、遺伝子だけではなくて育った環境が大きく影響を与えるという反論があります。
そして特に幼児期の環境の質が成人後の人生に大きく影響するそうです。
幼児期の介入(に関わらず様々な教育プログラム)には費用がかかるが、他の職業訓練や囚人の社会復帰プログラムなどと比べるとその損失はより多くの利益を生むということです。
ペリー就学前プロジェクトとは
1962年から1967年にミシガン州で低所得でアフリカ系の58世帯の子どもを対象に実施された。就学前の幼児に対して、毎日2時間の授業を受けさせ、週に1度は教師が家庭を訪問して90分の指導をした。指導内容は子どもの年齢と能力に応じて調整され、非認知的特質を育てることに重点を置いて、子どもの自主性を大切にする活動を中心としていた。毎日の復習は集団で行われ、子どもたちに重要な社会的スキルを教えた。就学前教育は30週間続けられ、終了後、これを受けた子どもと受けなかった子ども(対照グループ)を40歳まで追跡調査した。
アベセダリアンプロジェクトとは
1972年から1977年に生まれた、リスク指数の高い家庭の恵まれない子ども111人を対象に実施された。実験開始時の対象者の平均年齢は生後4.4か月だった。対象の子どもが8歳になるまで毎日介入し、プロジェクトが継続された。子どもたちは21歳になるまで継続して調査され、30歳の時点の追跡調査が2012年初めに実施された。
ペリー就学前プロジェクトの被験者になった子どもは当初はIQが高くなったが、その効果は薄れていき、介入が終わって4年が経つとすっかり消えたということ。
それに対してIQ以外の非認知能力等については効果は継続したということ。
つまり、目に見えて習得できることは、時間が経てばどっちにしろ周りの子どもも身に付けていくから、そこに一喜一憂するのはナンセンスだといえるのではないでしょうか。
今の子どもたちが本当に身に付けてほしい能力、非認知能力や他者を思いやる心、社会性というような能力を培うためには、幼少期の大人の適切な関わり方が非常に大切だといえるのではないでしょうか。
今の子どもたちが大人になる頃には、今ある仕事の半分がコンピューターやAIにとって代わられると言われています。
そのような時代に必要なのは、IQが高いだけではなく、自分の力で問題を見つけ出し、それを解決する手段を考え出すことのできる創造的な力です。
それが、当事者である子どもたちのみならず、その子どもたちが暮らす国の財源を確保し、未来への経済成長へと繋がっていくのです。
カンボジアのある村に目をやる
孤児院に預けられる子どもたち
私が暮らしていた4,5年前、カンボジアには孤児院がたくさんありました。
孤児院と聞くと両親がいないために、孤児院に預けられたのだと想像してしまうことが一般的です。
カンボジアの孤児院には次の3つの理由で孤児院に預けられます。
①両親または家族が子どもを養うことが難しい
②両親または家族が子どもに暴力を振るったり適切に育てるすべを知らない
③両親または家族がいない
圧倒的に多くの場合は①の経済的な理由です。
孤児院に預けられる年齢も様々です。
孤児院には様々な運営の仕方がありますが、私が知っているところは、どこも孤児院の運営者が預かった子どもに制服や教科書を用意し、教育を受けさせ、より良い将来を送らせたいと願っていました。
しかし孤児院に預けられる人数には限りがあります。
預けたくてもそれができず、貧しい家族とその日1日を暮らすために精一杯だという子どもは数え切れないほどいるでしょう。
一度、孤児院の子どもが生まれ育ったという村を訪問したことがありますが、子どもたちがたくさん暮らしていました。
そのときは子どもたちに渡す食べ物や文房具などを持っていきました。
このような背景を知ると、孤児院に預けられた子どもはまだ将来への道が拓けるため、幸せなのではないかと思います。
基本的には孤児院で大人が、生活や教育面に介入して、その子が一人前になって巣立っていくまで見届けます。
孤児院から家族のいる村に帰る
ところが孤児院に預けられた子どもは一安心とはいかないのが現実問題としてあります。
孤児院で中学生ぐらいまでを過ごした子どもが、急に家族の元へ帰るということが起こります。
高校生ぐらいの年齢になると、その子どもは働いてお金を稼ぐことができるようになります。
つまり家族のために働き手となることができるのです。
その頃の子どもをまた村に引き取って、家族がその日生きていくための仕事に就かせます。
幼少期を孤児院で過ごし、学校へ行くことのできた子どもは、村に戻った後、家族のために毎日働きます。
中学卒業程度の子どもが就くことのできる、カンボジアの農村の仕事は本当に限られていることでしょう。
私の知る限りでは、その日暮らしの生活に戻る子どもたちの話ばかりです。
プロジェクトの効果よ全ての子どもたちへ
このペリー就学前プロジェクトやアベセダリアンプロジェクトの示す通り、幼少期の介入が子どもの人生に影響を与えるのなら、農村に戻った子どもたちはどのような行動を起こすのでしょうか。
幼少期もしくは学童期に孤児院で過ごし、適切な大人の介入によって学ぶことの大切さを知った子どもたちは、きっと農村に戻っても家族の手伝いをしながら、学ぶことへの意欲を忘れず、チャンスがきたときにそのチャンスを掴み取れるような子どもたちであってほしいと願います。
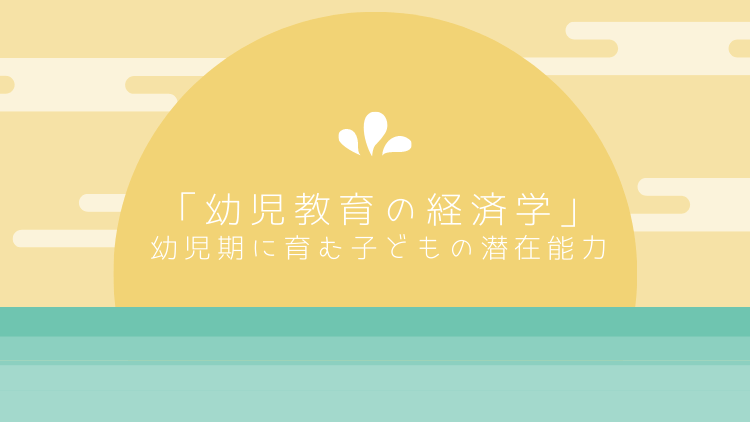
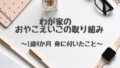

コメント