そのエコー写真はほとんどが黒くて、ただ真ん中に白い輪郭の丸いものが写っていた。
私の話をよく聞いて、丁寧な説明でいつも不安を取り除いてくれるそのお医者さんが、私の赤ちゃんだよと言って見せてくれた。
これが自分の中に新たな命が宿っていることを確認した瞬間。
自分のような不完全な人間が、一人の人間を育てるなんて、そんなことできるはずがないとずっと思っていたのは10代の頃から26歳ぐらいまで。
結婚したいとか子どもが欲しいとか、全く思わない人間だった。
そんな自分が、将来叶うなら自分の子どもを育てたいと考えるようになったのは、やっぱりカンボジアがきっかけだった。
2年半のカンボジアでの生活の中で、100人を超える子どもたちを見てきた。
貧しい村に暮らす子どもたちの中にも、貧困の格差があった。
親の子育てを見ないで育った子どもが親になったとき、その親は子育てのやり方がわからないということを知った。
自分自身が読み書きできないとき、それを子どもに教えることができないことを目の当たりにした。
読み書きどころか、トイレの行き方や人の話の聞き方を知らなかった。
貧しい村よりももっと貧しい村から出てきた子どもに、人の話の聞き方から鉛筆の持ち方、色の塗り方、歌の歌い方などを教えて半年ぐらいが経ったとき、その子どもたちの親が私のことを見ていた。
ある日、私がやるようにその親は自分の子どもにカンボジアの言語であるクメール語を少しずつ教え始めた。
見たことがなかったからやらなかっただけで、子どもを育てたいと思う親の気持ちや行動は、どんな環境にいても同じなんだということを教えられた。
親でない私ができることには限りがあった。
叱るという行為は愛があってこそ成り立つ。
親の前でその子たちを叱ることは躊躇われた。
その瞬間がまさに今までの考え方を大きく覆した瞬間だった。
「自分の子どもを育てたい。」
26歳だった。まだ遅すぎなかったみたいだ。
カンボジアから帰国して半年、日本での新しい生活に無我夢中で取り組み始めた頃、運良く生涯のパートナーと出会った。
そして30歳になったばかりで、初めて自分の子どもを出産した。
小さな命は一生懸命可愛らしい声で「ふにゃあ、ふにゃあ」と泣いて、私の目を釘付けにした。
小さな手には5本ずつ指がしっかりついていて、耳もちゃんと聞こえているようで、髪もふさふさと言っていいぐらいはえている。
本当にありがたいことに、五体満足で健康で元気な男の子が私の元にやってきた。
「私たち夫婦のところに産まれてきてくれて、ありがとう。」
その言葉に尽きると思った。


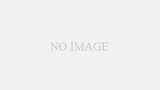
コメント